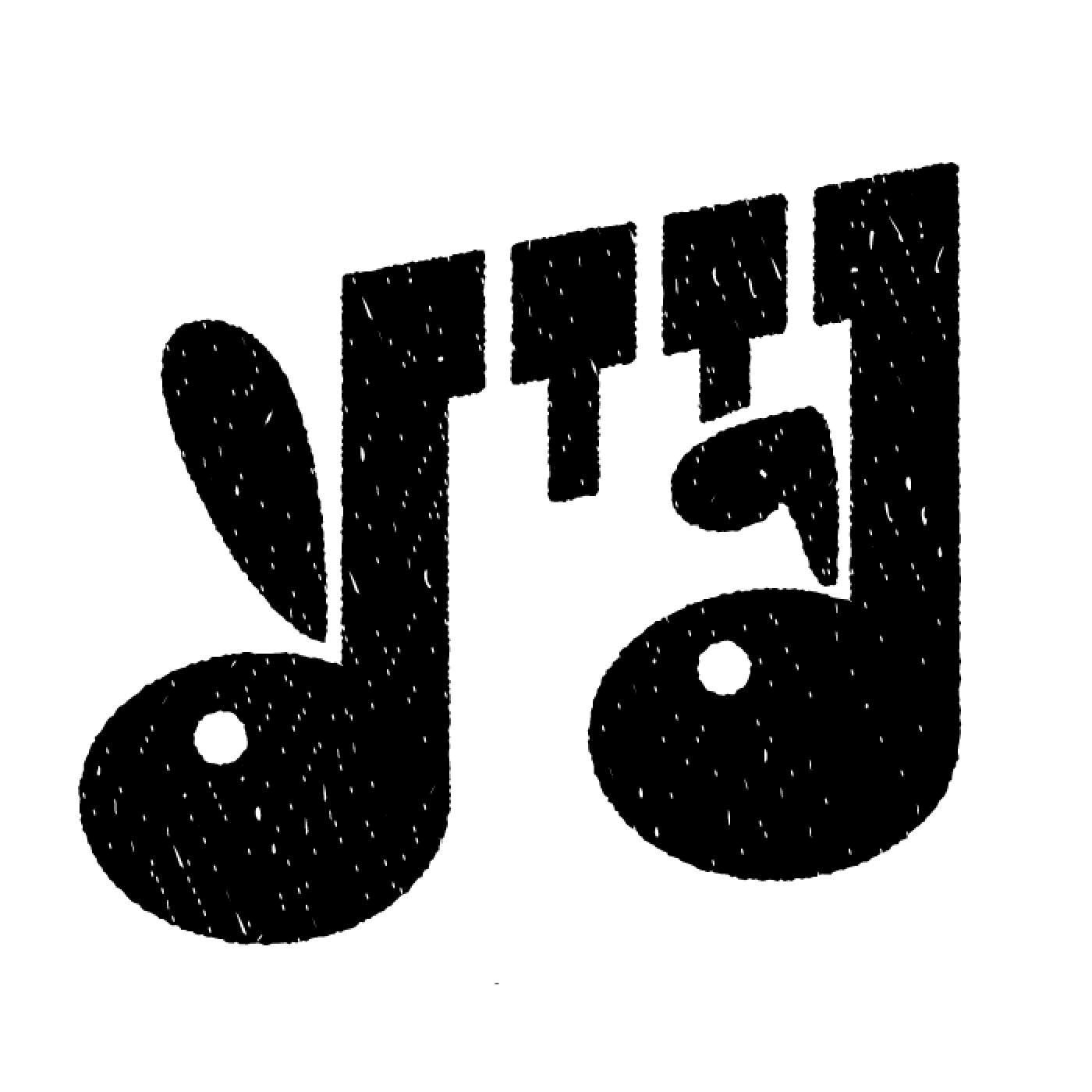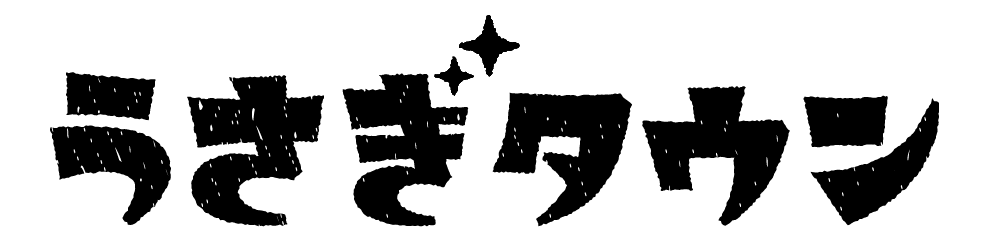再三再四
Chapter7
遠くもなく近くもない。言ってしまえば、論じるに値しない距離感。
であれば、やはりそれは遠い。
私は生来、そう感じることは無かった。
私が誰かに近づこうとすることはなかったし、誰かが私に近づこうとすることも、事実としてなかったからだ。
もちろん、私自身がそれを望んでいたのだから、不満は言うまい。
どうして望んでいたのか。
それは、あなたのような大切な存在が離れて行ってしまうことが怖いからだ。
私の母と私の父が幼い頃に他界してしまったという記憶は、そういう感情中枢にまで隙間なく絡みついているのだ。
きっとあなたはそれを知らないけれど、それでも、あなたは私に近づいてくれた。
近づくことを恐れる私に、あなたは触れてくれた。温かい指で、優しい眼差しで。
だから、途中から何となくわかってしまったのだ。
あなたの気持ちが。
これから、あなたが向かう場所が。
この物語の結末が。
「ここだよ」
衣料品専門の商店街を抜けて、道一本逸れた道路沿い。
こじんまりとした店構えながら、装飾にはヴィンテージ感漂う雑貨が並ぶ、いかにも洋風な建物。
客は少ないが活気はあるので、ピークの時間を外しているのだろう。
「お菓子屋さん、ですか」
世情に疎い私でも、この店は知っている。
テレビ番組でも何度か取り沙汰されていた。
そして、人々が何を求めてここを訪れるかも、もちろん知っている。
「少し、待ってて」
私が頷いて顔を上げたタイミングで、雪がはらりはらりと降って来た。
雪の降っている日は外出しないと思っていたはずなのに。
私は一体何を思って、何を期待して、今、寒空の下あなたを待っているのだろう。
罪悪に苛まれた良心か、それとも諦念にも似た妥協か、それこそ暖なのか。
正直、どれでもよかった。
願わくば、結末の見えている物語以外の続きを、私は所望していたのだが。
「お待たせ。はい。チョコ。わたしの手作り。本気のやつ」
「あ、ありがとうございます。手作り、ですか? お店のじゃなくて」
「ああ。ここ、わたしの家」
でも。
それなのに私は、この物語の続きが読みたかった。
「明日、日曜日だしさ。今日は泊まらない?」