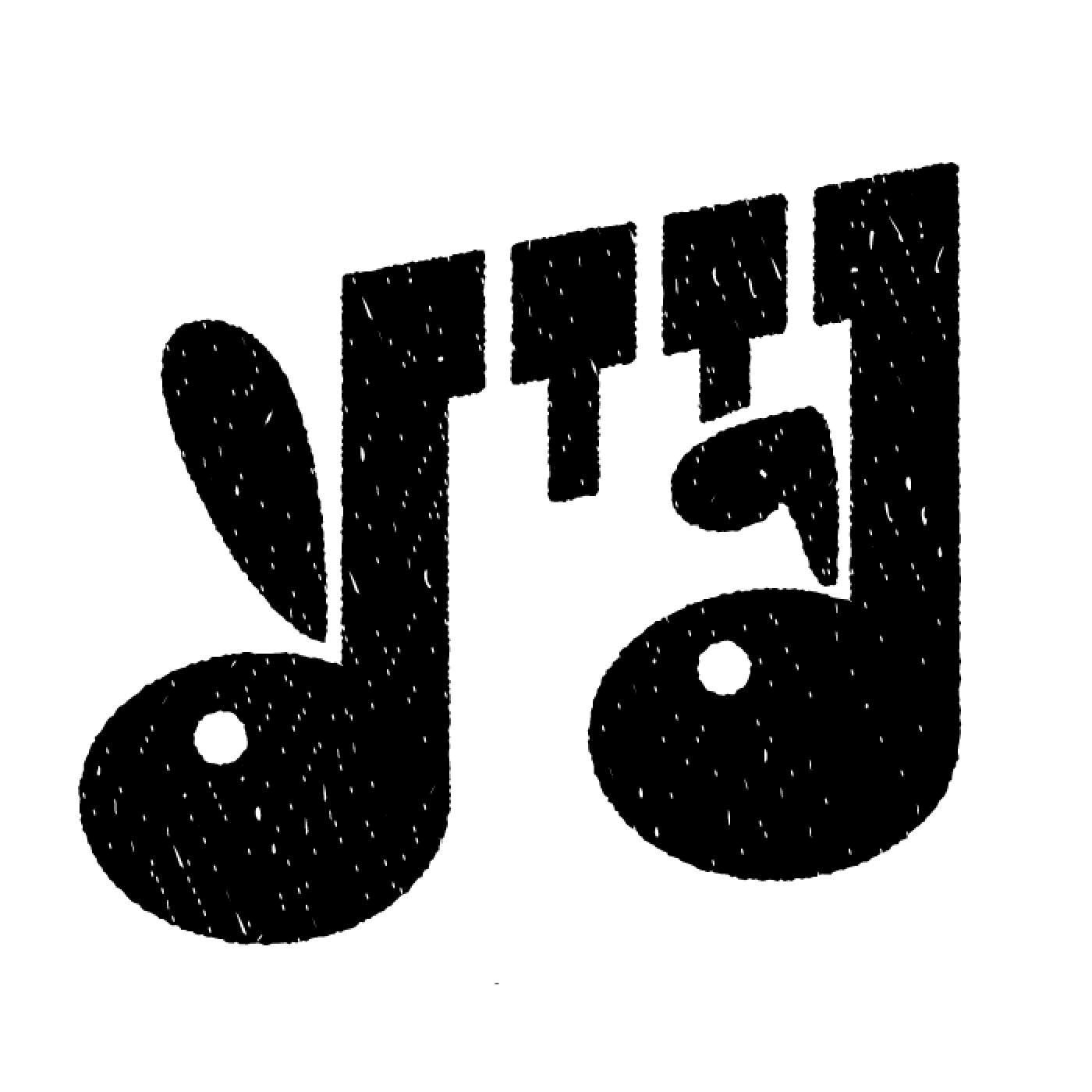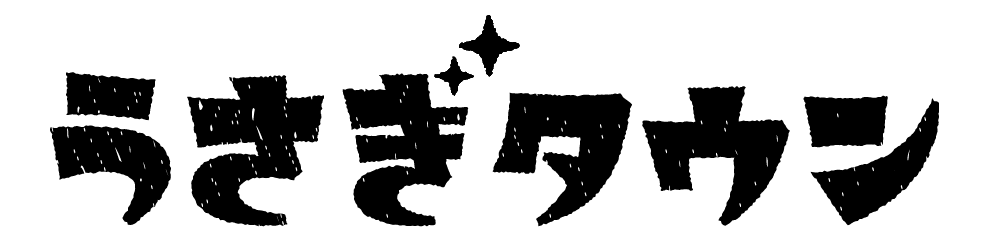再三再四
Chapter3
あなたはいつも優しくて、あなたのことを少し怖いなんて思っていた自分が本当に馬鹿みたいだ。「嫌い」なんてもってのほか。一緒にいて楽しいと思える人、何年ぶりにできたろう。
私は人付き合いが下手だと、私自身が暗示するけれど、そんなことは当然かもしれない。
何年振りかすら思い出せないくらい、すでに無頓着なのだから。
けれど、それでも、らしくもない前向き発言をしようとするなら、「これから、思い出を作ればいい」になることだろう。そういう意味ではもう、“はじめて”と言っても過言ではない。
たかが、一度ぶつかって、それが縁で教科書を貸しただけの関係で。
あなたは誰にでも優しいから、特別何とも思ってはいないのかもしれないけれど。
それでも、少なくとも私は、それくらいはあなたを好いていた。
「すごいですね。自分で作ってるんですか、お弁当」
「親が料理しないからねー」
こうしてあなたと一緒に昼食を食べる時間が、最近の私の楽しみであった。
昼食など一人でも摂れるけれど、あなたと食べる昼食はまた格別だった。
自分の中にあるわずかばかりの勇気がきっと、良いスパイスになっているのだと思う。
けれど、私のせいであなたの交友関係が破綻してしまわないか、不安はあった。
私に時間を割くということが、イコール「いつものグループから離れている時間」であることは、明々白々たる事実だからだ。同時に、私の「読書時間」も減っているわけだけれど。
「ねぇ。休みの日は何してるの?」
「えっ? あ、えと、学校の宿題です」
「違う違う。言うと思ったけどそうじゃなくて」
「あ、ごめんなさい。そうですね、本はよく読みます」
「うん。それも言うと思った。ははははっ! 外に出て遊んだりはしないの? ショッピングとかさ」
「ショッピング、ですか……? 私、あまり外出はしない、と思います」
「そっか。じゃあさ。今度の土日さ。二人でどこかに遊びに行かない?」
「わ、私と?」と訝ると、あなたは「それ以外に誰がいるの?」と言わんばかりに綽々と笑う。
「どうして?」とは聞かなかった。それを聞くことで傷つくのは、私だけではないと思ったから。
「わかりました……」と頷くと、食事が喉を通りづらくなった。
そうして、私の尊い読書時間は、あなたとの時間に変わる。
不思議と安堵の溜息が出る。
私は、私が「好き」な読書よりも、「嫌いじゃない」あなたをとってしまったのだ。