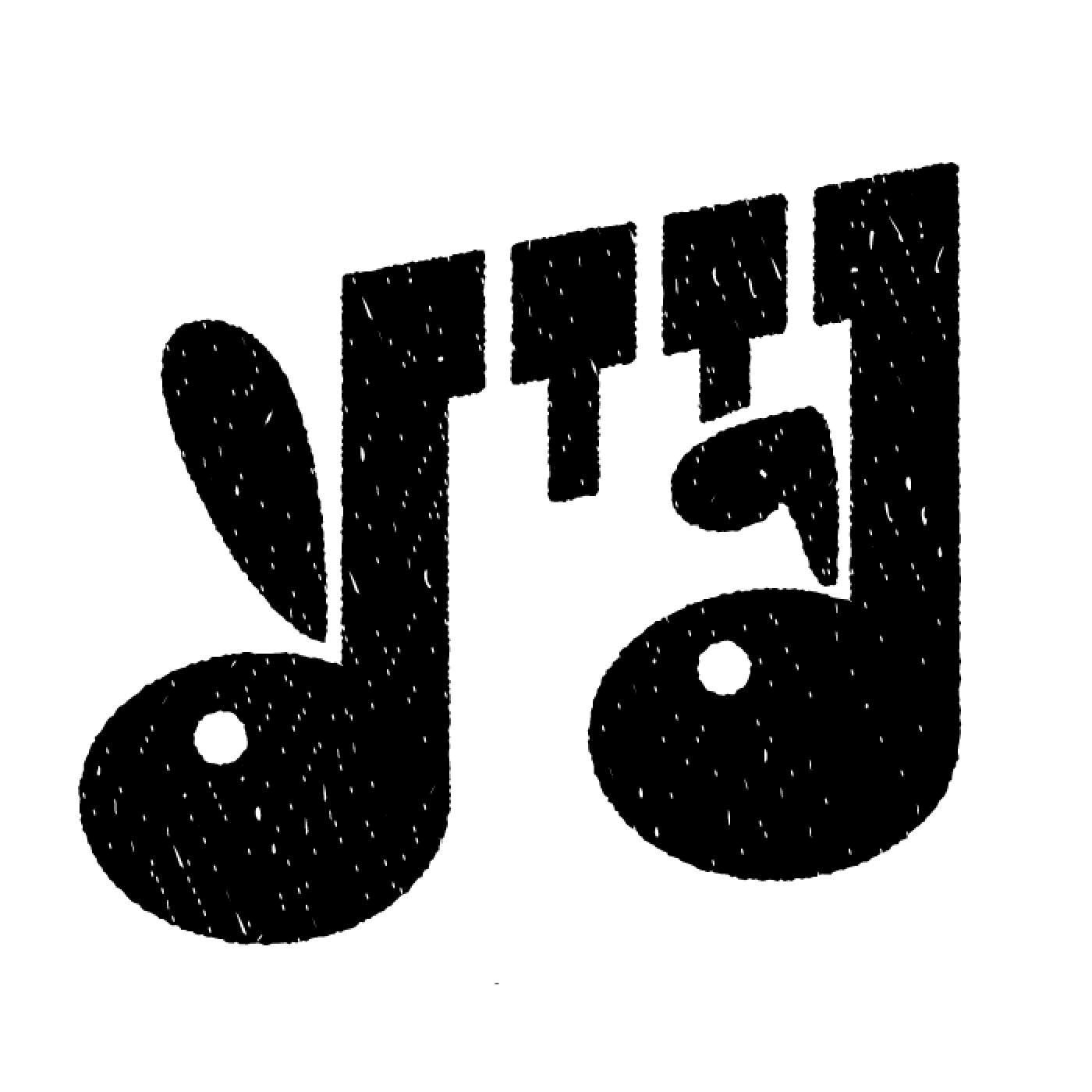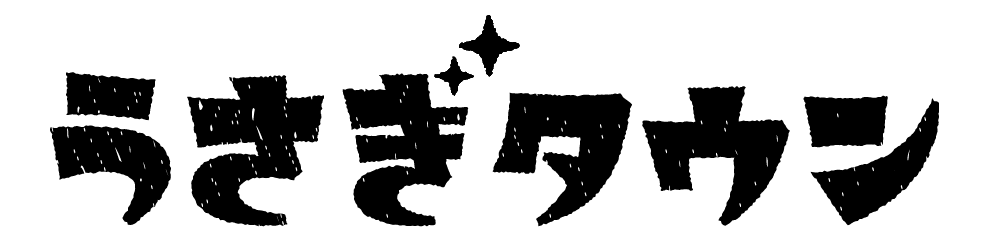一期一会
Chapter7
これが言うところの“ピロートーク”なんだろう、とやけに低いテンションでわたしは語れるようになった。
徐々に鎮まっていく呼吸も、夜も、わたしは好きになれそうもない。
何だか、終わりがすぐ近くにありそうで、怖くなるのだ。
「梓」
「ん?」
布団の擦れる音と同じか小さいくらいの声で、葉月が囁く。
時折窓を叩く夜風よりも、その声にずっと安心した。
「梓は子ども、好き?」
「えっ……」
「変な意味は無い……と言ったら嘘になるけど、そこまで深くはないと思う」
「まぁ、好きかな……」
控えめに言うけれど、その程度は控えめではなかった。
実は、小さい頃の将来の夢が保育士だったし。それがダメならお菓子屋で。
でも、それを聞くってことは、やっぱり……。
「好き、ですか……。ですよね。そんな気はしていました」
「えっと……ごめん」
当然、わたしたちの身体では、それはできない。
だから子孫がどうとか言われるわけだし、そもそもそういうものじゃないから気持ち悪いって揶揄される。
そういう覚悟で付き合ってるから、罵倒されるのはどうってことはない。
けど、それ以前に、当人たちの気持ちの問題があるのだ。
すごく、すごく、難しいことだ。好きと口にするのは、こんなにも簡単なのに。
だから、そういう問題で別れるのだけは、わたしは嫌だ。
別れる時はせめて、ちゃんと嫌われたい。
けど、今は大好きだから ―― そういう想いをぐんと伸ばして、わたしは葉月の頭を撫でた。
「ありがとうございます。けど、大丈夫です。私も、好きですから」
「葉月……」
「だから、少し考えたんです。これからのこと」
「これから……ね」
何だろう。暗い話だと思っていたんだけど、葉月の表情は清々しく透き通っていた。
月光に照らされているからか、美肌の湯の効能か、それとも……。
葉月の微笑みは、葉月の好きな小説で言うところの“新刊”が出た時に似ていた。