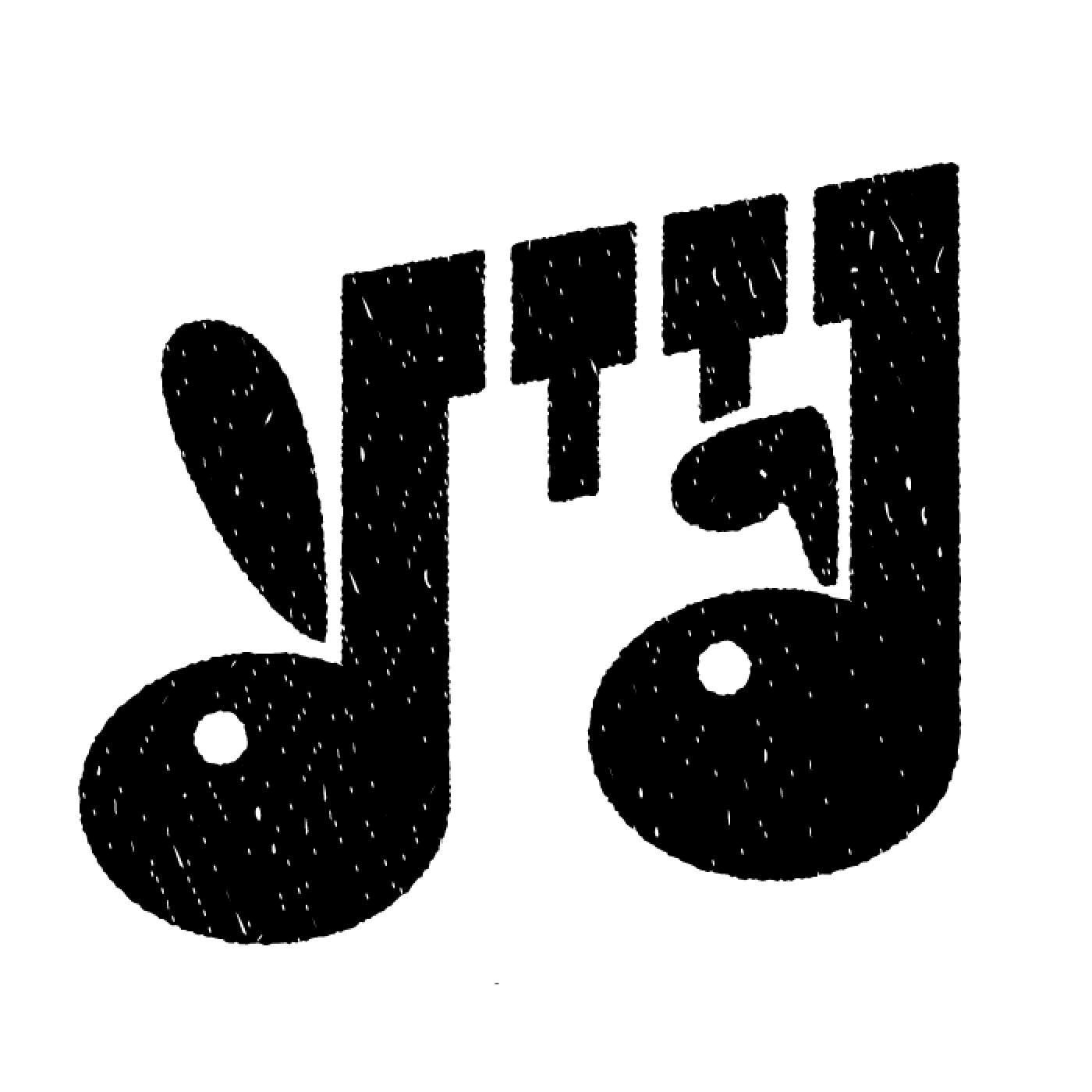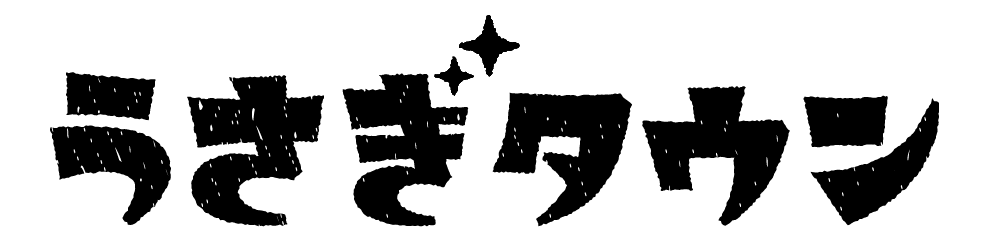一期一会
Chapter2
「付き合う」という言葉で検索エンジンをかけたのは、多分に、私の方が早い。
あなたが私にそれを告げる前にそうしていたのなら、話は別になるけれど。
私自身、何かを期待して調査したわけではないのだ。
ただ、悲しい記事であろうと嬉しい記事であろうと、あなたの知っていることなら私も知りたいと思ったから。
どんな参考書にも辞書にも載っていない、“宮川梓”という存在のことを。
「付き合う」ことについてわかったのは、幸いにも悪いことばかりではなかった。
私たちだけに限った話なのだと思っていたが、あるところにはあるらしい。反対する者は確かにいるけれど、そうしない者も中にはいるようで。少なくとも「病気」なのではないのだとわかったから、収穫だと思いたい。
最後に「子供」というワードが目に入ったところで、私はネットサーフィンをやめた。
今は未来よりも、目の前の物語を読みたいのだ。
出来ることなら、毎日新刊の出る喜びを、梓にも。
「葉づ……ごほごほっ。ふ、藤森さん? 今日どう、一緒に帰らない?」
「いいですよ。宮川さん」
視線を合わせないで、さも他人のように振る舞って。お互いにたまたま用事が無くて、一緒に帰るような友人が誰もいない偶然も合わさって。運よく隣の席に座っていて、これから帰る方向は途中まで同じ。
そういう命運を、私は「主人公みたいだ」と評し、時々思い出して笑う。
「どっちがだ」という隠せない想いは、この距離に寓してしまって。
私は、私たちは校門を出る。
暫く進んだところで、梓はいつも嘘をつく。
「そろそろ、寒くなってくるよね……」
手袋よりもマフラーよりも温かいものを覚えてしまった私は、きっと。
きっと、今より前に進めない。